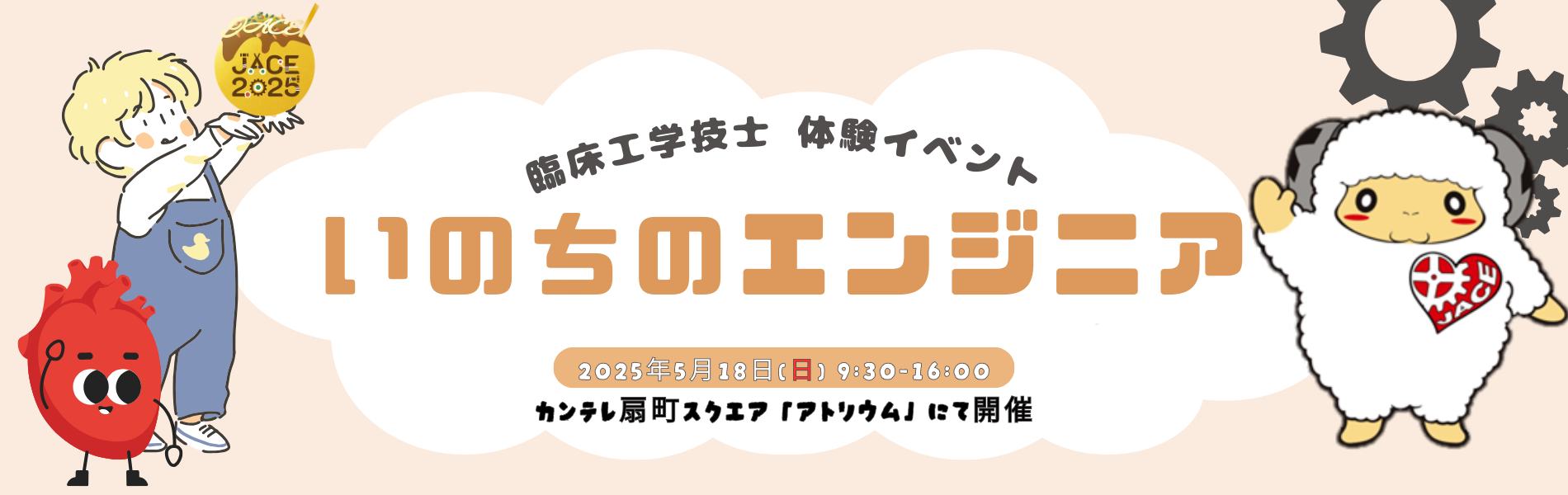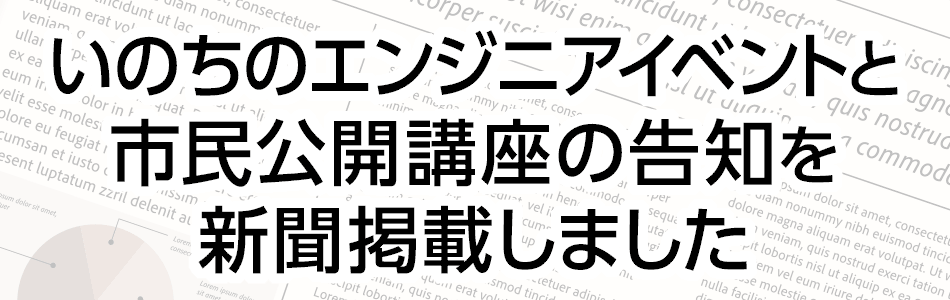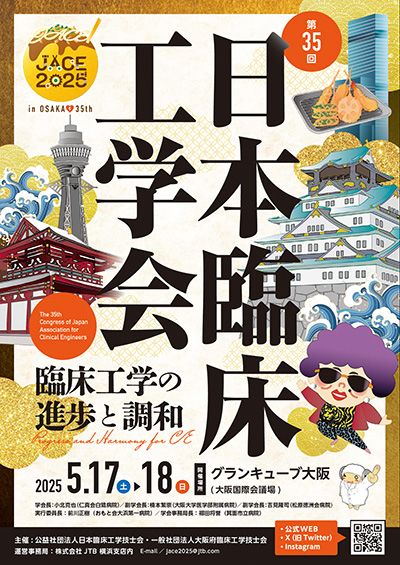パネルディスカッション21〜31
パネルディスカッション21
5月17日(土) 15:45〜17:45 第17会場(12F/特別会議場)
臨床工学技士が担う医療安全
座長小林剛志(平塚共済病院 臨床工学科 公益社団法人 日本臨床工学技士会)
座長松田晋也(東京都済生会向島病院 医療安全管理室)
PD21-1本間 崇(公益社団法人 日本臨床工学技士会 善仁会グループ)
PD21-2松村由美(京都大学医学部附属病院 医療安全管理部)
PD21-3遠藤弘子(大阪公立大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部/看護部)
PD21-4小林剛志(平塚共済病院 臨床工学科 公益社団法人 日本臨床工学技士会)
今期から本委員会は、担当副理事長・担当常任理事・委員長のすべてが入れ替わり新たにスタートしている。現在、臨床工学技士の医療安全の確立をすべく教科書の作成(案)や各関係学会等との連携をより密にし、臨床工学技士へ安全文化を根づかせるための教育や体制の構築に取り組もうとしている。今回の大会では、他団体の医師・看護師の意見も交えながら今後の本委員会に必要なこと、臨床工学技士が担うべき医療安全を議論していく。新体制スタートにふさわしい演者の先生方を選出させていただいており、必見の企画である。
パネルディスカッション22
5月18日(日) 13:10〜15:10 第1会場(5F/大ホール)
地域医療構想実現にむけた臨床工学技士の集中治療業務の実際
座長平山隆浩(岡山大学学術研究院 医歯薬学域 地域二次救急・災害医療推進講座 日本臨床工学技士会集中治療業務委員会)
座長相嶋一登(横浜市立市民病院 臨床工学部)
PD22-1奥田晃久(公益社団法人 日本臨床工学技士会)
PD22-2大橋利成(社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 臨床工学科)
PD22-3河岸愛理(医療法人澄心会 岐阜ハートセンター 臨床工学科)
PD22-4渡邉研人(JCHO 東京山手メディカルセンター)
PD22-5高木俊介(横浜市立大学附属病院 集中治療部)
本邦は超高齢化社会であり、人口減少も著しい。これまで行われてきた医療体制では経営・人員的にも厳しい状況にある。都道府県は病床機能報告による各医療機関の病床数を照らし合わせ現行の病床のあり方を望ましい方向に導くための地域医療構想を策定している。そして、多くの二次医療圏では高度急性期、急性期の病床は2025年には現状では過剰になるとされている。急性期で高いニーズがある生命維持装置の操作、保守管理、教育を生業としている臨床工学技士にとっても大きな影響がある。病床機能の特定集中治療室管理料の算定区分変更や病院統合、医療機器の更新費用の捻出が困難、人員削減など様々な課題が出ている。
本セッションでは急性期・回復期病院クラスにおける集中治療業務を取り巻く現状を様々な角度から議論したい。
パネルディスカッション23
5月18日(日) 10:05〜11:35 第2会場(5F/小ホール)
VA管理の最近のトピックスと未来展望
座長人見泰正(桃仁会病院)
座長村上 淳(東京女子医科大学附属足立医療センター 臨床工学部 日本血液浄化技術学会 VA管理検討委員会)
PD23-1延命寺俊哉(桃仁会病院 医療技術部 臨床工学科)
PD23-2小林大樹(大阪けいさつ病院 バスキュラーアクセスセンター)
PD23-3村上 淳(東京女子医科大学附属足立医療センター 臨床工学部 日本血液浄化技術学会 VA管理検討委員会)
PD23-4松田政二(どい腎臓内科透析クリニック 臨床工学部 (一社)日本血液浄化技術学会 VA管理検討委員会)
VAエコーやVA管理・モニタリングの次世代の手法や今後の展開について議論できる場を作りたい。また、ここ数年で新たに提唱された指針や資格についての知見を紹介して共有する場としたい。
パネルディスカッション24
5月18日(日) 13:10〜14:40 第10会場(10F/会議室1003)
CEが関わった人工呼吸療法の難渋症例
座長荒田晋二(JA 広島総合病院 臨床工学科)
座長田中勇真(大阪大学医学部附属病院 臨床工学部)
PD24-1山下大輔(熊本大学病院 医療技術部 ME 機器技術部門)
PD24-2窪田史子(社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 診療技術部 臨床工学室)
PD24-3谷 亮太(JA 愛知厚生連 豊田厚生病院 臨床工学室)
PD24-4大谷昇平(地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 臨床工学室)
人工呼吸療法においてCEも関わっている施設の人工呼吸管理の過程において、管理に難渋する症例もあり、各施設において奮闘しているのではないか。その過程は多くの選択肢があり、その選択に各施設が多職種と協力して問題解決に取り組んでいる。
本セッションでは、CEの人工呼吸管理の関わり方やRST活動を通じて、難渋症例にどのように関わっているか、その体験談を各施設から報告していただき、次に直面する難渋症例に対応する一案となれるような内容にしていきたい。
また、それらの施設がどのように他職種と共同しているか、その工夫や苦悩も含めて発表していただく。
パネルディスカッション25
5月18日(日) 9:35〜11:35 第13会場(10F/会議室1008)
何ができる?!呼吸療法におけるCEの臨床業務
座長沖島正幸(JA 愛知厚生連 豊田厚生病院 臨床工学室)
座長玉元由果莉(社会福祉法人 大阪暁明館 大阪暁明館病院)
PD25-1荒田晋二(JA 広島総合病院 臨床工学科)
PD25-2益田一輝(神戸大学医学部附属病院 臨床工学部)
PD25-3李 彩聖(JA 茨城県厚生連 総合病院 土浦協同病院 臨床工学部)
PD25-4山門俊紀(大阪府済生会富田林病院 医療機器管理室)
PD25-5陶山真一(社会医療法人 元生会 森山病院 検査部)
現在、タスクシフト/シェアが推進されているなか、医療機器の保守業務以外の呼吸療法の「臨床業務」について、今後どのような業務がタスクシフト/シェアできるかを総合討論する。また、呼吸療法業務における病院間格差の現状と課題を明らかにし、種々の施設から見た価値を知ることで自施設にフィードバックしたい。
同じ呼吸療法でありながら施設間で呼吸療法業務の内容は大きく異なる現状があるため、それぞれの状況を共有したうえで実践的な課題解決を会場からの意見も取り上げディスカッションしていきたい。そして、今後タスクシフト・シェアに関する呼吸療法業務について、大病院だからできる臨床業務、中小規模病院だからできる臨床業務のを検討していきたい。
パネルディスカッション26
5月18日(日) 9:35〜11:35 第14会場(10F/会議室1009)
多様な開発支援体制で医療機器開発を"デザイン"する臨床工学技士
座長篠原智誉(医療法人社団志高会 三菱京都病院)
座長吉田幸太郎(神戸大学医学部附属病院)
PD26-1村垣善浩(神戸大学大学院 医学研究科)
PD26-2穴井博文(大分大学 医学部先進医療科学科)
PD26-3小野淳一(川崎医療福祉大学 医療技術学部臨床工学科)
PD26-4片岡 怜(国立成育医療研究センター 手術・集中治療部 医療工学室)
コメンテーター西藤真太郎(経済産業省 近畿経済産業局 地域経済部 バイオ・医療機器技術振興課)
コメンテーター仲條麻美(順天堂大学)
コメンテーター井桁洋貴(飯塚病院)
コメンテーター石田幸広(株式会社セカンドハート)
コメンテーター関根広介(医療法人鉄蕉会 亀田総合病院)
臨床現場での経験と自身の専門知識を生かして医療機器の開発に挑んでみませんか?
本セッションでは医療機器開発をデザインし、研究開発やアイディアを形にして製品化するための道のりについて様々な立場、背景から具体的事例を交えて紹介します。
多様な関係者との連携による「支援」やその体制を知ることは、臨床工学技士が医療機器開発を進める上で立ちはだかる様々な壁(資金調達、技術的な課題、規制や知財、マーケティング、上市への促進)を乗りこえるための鍵となり、臨床工学技士のキャリアアップにつながるヒントにもなることでしょう。
医療の未来を創る第一歩を踏み出し、社会に貢献するチャンスを掴みましょう。
パネルディスカッション27
5月18日(日) 13:15〜15:15 第14会場(10F/会議室1009)
迫りつつある南海トラフ地震への準備状況
座長森上辰哉(日本臨床工学技士会)
座長西村典史(日本臨床工学技士会)
PD27-1鈴木教久(独立行政法人国立病院機構本部DMAT 事務局)
PD27-2古下尚美(大阪府健康医療部保健医療室地域保健課)
PD27-3三井友成(日本臨床工学技士会 災害対策委員会)
PD27-4山家敏彦(神奈川工科大学 健康医療科学部臨床工学科 日本災害時透析医療協働支援チーム(JHAT))
PD27-5村上 豪(大阪市水道局 総務課)
PD27-6井上勝哉(臨床工学技士(防災士))
南海トラフ地震の注意発出があり、迫りつつある地震に対して準備状況を確認する。
パネルディスカッション28
5月18日(日) 8:30〜9:30 第16会場(12F/会議室1202)
もうかりまっか?ぼちぼちでんな、を理解する。
座長西岡 宏(国立循環器病研究センター)
座長秋田展幸(鈴鹿医療科学大学)
演者高田茂和(仁真会 白鷺病院)
演者柏原 謙(京都桂病院 臨床工学科 脳卒中センター脳神経外科 心臓血管センター内科)
演者近藤智勇(国立循環器病研究センター)
演者高田敏也(松原徳洲会)
演者村中秀樹(社会医療法人生長会)
臨床工学技士の業務は組織横断的に多岐にわたる。
手技料(診療報酬)や取り扱う材料により病院経営に響く部分は多々あり、我々臨床工学技士はコスト意識を十分持たなければならない。
しかしながら、コスト意識を!と言われるものの一部の管理職等を除いて、実務をこなしている新人や中堅はどこまでがDPC(診療群分類包括評価、そもそもDPCとは?)なのか、また臨床工学技士としてどの部分で経営を潤わせているか、何が収益を減らしているかを理解している人は非常に少ない。
そこで大阪ならでは?のちょっぴり下世話なお金の話ではあるが、透析、手術室や呼吸、カテ、体外循環など各分野の方に登壇頂き、どの部分で点数(お金)を稼いでいるのか実例等を上げて講演頂く。
パネルディスカッション29
5月18日(日) 9:35〜11:05 第16会場(12F/会議室1202)
全国災害対策万博
座長白井勇希(大阪赤十字病院)
座長佐藤 豊(仙台赤十字病院)
演者岡本裕美(東邦大学医療センター大橋病院)
演者安田栄吉(社会医療法人明生会 明生第二病院)
演者宮本照彦(中央内科クリニック)
演者小川晋平(医療法人尚腎会高知高須病院)
演者黒田彰紀(熊本赤十字病院)
昨今、日本では大規模自然災害に見舞われる事が多くなっている。2024年8月8日、日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震発生に伴い、同日、気象庁より南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された。幸いにして、巨大地震は発生しなかったものの、医療分野においても災害対策の重要性が増してきている。
今回、医療分野における災害対策の現状や問題点を日本全国各地域の臨床工学技士会の担当者より講演していただき、現状の対策や過去の経験からの教訓、また問題点を共有し、災害対策の推進、啓蒙に繋げていきたい。
パネルディスカッション30
5月18日(日) 8:30〜10:00 第17会場(12F/特別会議場)
本音で語ろう!在宅人工呼吸療法の進歩 〜臨床工学技士と医療機器メーカーとの調和を目指して〜
座長平野恵子(JA 広島総合病院 臨床工学科)
座長宮内昭吾(社会福祉法人 向陽会)
PD30-1平野恵子(JA 広島総合病院 臨床工学科)
PD30-2津藤 保(医療機器公正取引協議会)
PD30-3野口恭平(恩賜財団済生会横浜市東部病院 臨床工学部)
PD30-4塚田さやか(公立陶生病院 臨床工学部)
PD30-5及川秋沙(独立行政法人国立病院機構岩手病院 臨床工学室)
在宅人工呼吸療法は、以前は主に医師と医療機器メーカーで行われていましたが、2008年の立ち入り規制以降、CEが介入を開始した医療機関も増えています。業務実態調査においても在宅移行支援に携わるCEは増加傾向で役割が確立されつつありますが在宅移行後も継続的に関与しているCEは少なく、医療機器メーカーにフォローを依頼していることも現状です。
人工呼吸器は生命維持管理装置であり、メーカー介入が制限された今患者の呼吸状態の変化を適正に管理できているのでしょうか?一方で大規模災害の際、医療従事者だけで患者の安全を確保できるのかという課題もあります。今回、CEと医療機器メーカーの立場で現状を共有することで、役割分担を明確にし、安全な在宅人工呼吸療法提供のためにどう介入するべきかディスカッションを行います。
パネルディスカッション31
5月18日(日) 10:05〜11:35 第17会場(12F/特別会議場)
全世代が意欲的に参加できる生涯教育制度を目指して~ICT活用による取り組みと今後の展開~
座長鈴木雄太(東北大学病院)
座長梅田千典(自治医科大学附属さいたま医療センター)
PD31-1鈴木理功(帝京大学 福岡医療技術学部 医療技術学科 臨床工学コース)
PD31-2工藤元嗣(日本医療大学 保健医療学部 臨床工学科)
PD31-3肥田泰幸(東都大学 幕張ヒューマンケア学部 臨床工学科)
現在、生涯教育委員会では、会員の学術的研鑽を支援や臨床工学技士の専門性の向上を目指して、生涯教育制度の構築を行っている。2023年度4月よりICTを活用した生涯教育制度がスタートし、現在(2024年12月時点)までに入会オリエンテーション2432名、臨床工学技士基礎研修会1358名の会員が受講を完了し、多くの会員において好評を得ている。今後も、多くの会員にこの生涯教育制度を活用してもらうために、さらなる生涯教育制度の周知と新たな生涯教育制度の展開の必要性を感じている。そこで、本セッションでは、現在の生涯教育制度の概要や今後、予定されている新たな展開について解説する。また、総合討論では、全世代が意欲的に参加できる生涯教育制度を目指し、会場の皆様と共に、ディスカッションを展開していきたい。