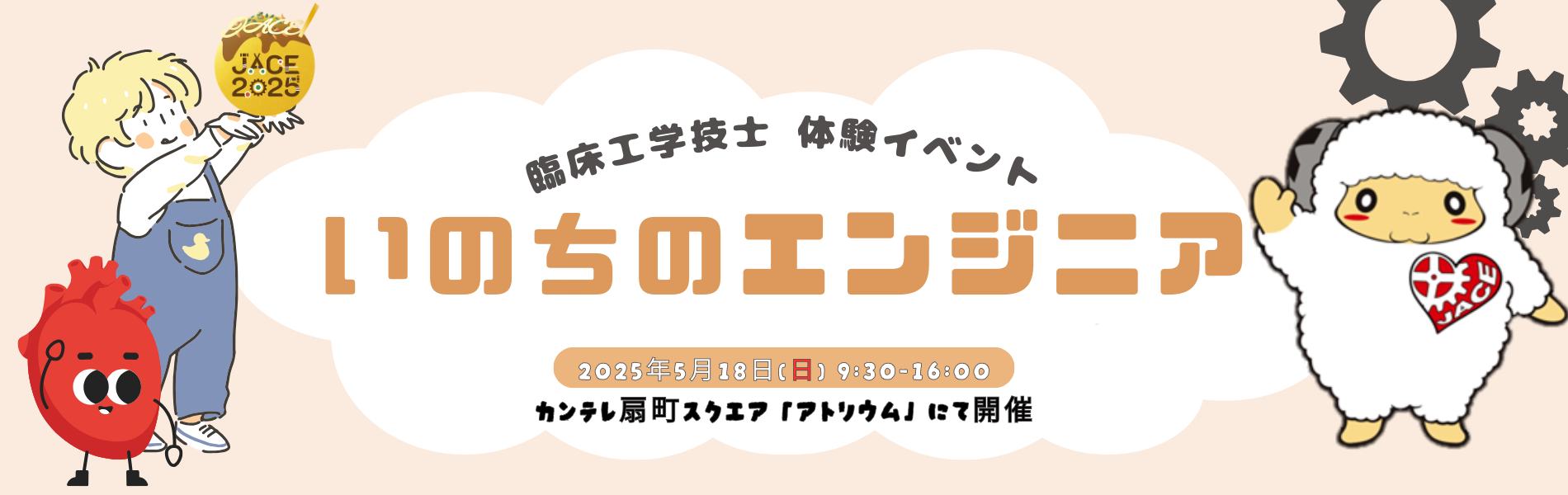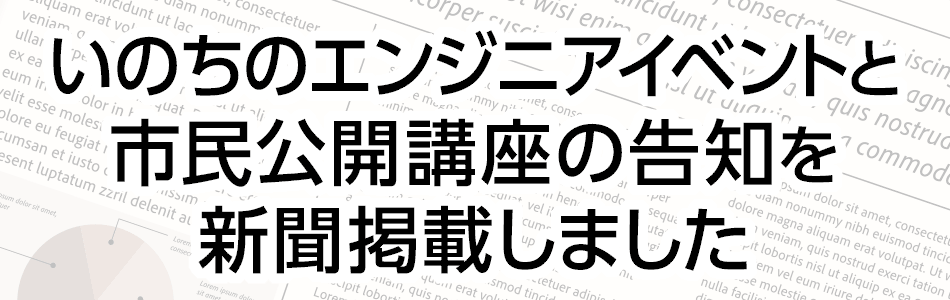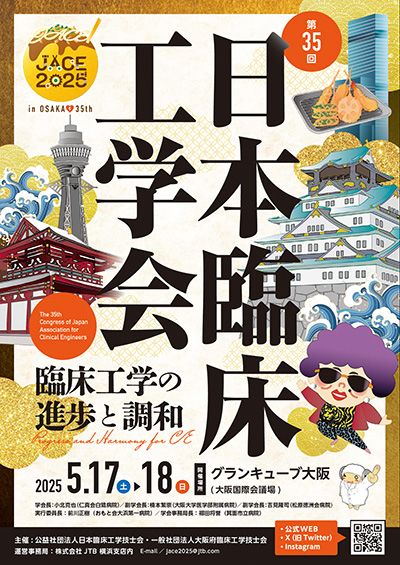パネルディスカッション11〜20
パネルディスカッション11
5月17日(土) 13:40〜15:40 第12会場(10F/会議室1006・1007)
論文執筆をはじめから丁寧に~論文執筆のエキスパートが日頃のお悩み解決します!~
座長藤井清孝(北里大学 医療衛生学部 医療工学科 臨床工学専攻)
座長三木隆弘(日本大学病院 臨床工学室 技術長補佐)
PD11-1藤井清孝(北里大学 医療衛生学部 医療工学科 臨床工学専攻)
PD11-2小野弓絵(明治大学 理工学部)
PD11-3大石 竜(昭和医科大学 統括臨床工学室 昭和医科大学大学院 保健医療学研究科 医療技術分野 臨床工学領域 公益社団法人 日本臨床工学技士会 学術機構運営委員会)
学会発表は数多くおこなっているものの、論文執筆となるとハードルが高いと感じる方は多くいらっしゃるのではないだろうか。学会発表を単純に肉付けし文書化しただけでは、論文化は難しい。その原因は、臨床業務のガイドライン等と同様に論文執筆にも明確な“お作法”があり、その遵守が厳しく求められるためである。本セッションでは、決して簡単ではない論文執筆について、はじめから丁寧に説明するとともに、日本生体医工学会「生体医工学」編集長と日臨工学術機構運営委員会が、その経験から得られた“コツ”を伝授する。その後のディスカッション時間にて会場の皆様からの質問時間を設けているため、是非、論文執筆に関する日頃の悩みを解決して頂きたい。
パネルディスカッション12
5月17日(土) 9:00〜10:30 第13会場(10F/会議室1008)
Clinical Engineer’s Horizon : 新たな領域へのチャレンジと未来への可能性
司会小笠原順子(弘前大学医学部附属病院)
司会梶原吉春(社会医療法人財団大和会東大和病院)
演者高根麻央(交雄会新さっぽろ病院 臨床工学室)
演者西谷光広(だいもん内科・腎透析クリニック 臨床工学科 技士長)
演者土居二人(長崎総合科学大学 工学部医療工学コース)
これまでの領域拡大委員会における活動内容を振り返りながら、臨床工学技士の業務領域をさらに拡大する可能性について検討する場とする。本セッションでは、委員4名がこれまでの取り組みについて報告し、臨床工学技士が活躍可能な新たな分野や、業務領域拡大のために取り組むべき課題について発表を行う。さらに、パネルディスカッションを通じて、参加者からの意見やアイディアを広く募り、委員と共にこれからの展望について議論することで、実現可能性の高い新たな領域の開拓に向けた具体的な方向性を探ることを目的とする。
パネルディスカッション13
5月17日(土) 10:35〜12:05 第13会場(10F/会議室1008)
ハイパーサーミア導入施設の普及促進に向けて
座長濱田祐己(広島県立二葉の里病院 臨床工学科)
座長三浦ゆかり(社会医療法人 禎心会 札幌禎心会病院)
PD13-1加藤恭浩(社会医療法人厚生会 中部国際医療センター 臨床工学技術部)
PD13-2古谷昭人(島根大学医学部附属病院 医療機器診療支援センター)
PD13-3元村哲也(原三信病院 臨床工学科)
PD13-4大田 真(社会医療法人北斗 北斗病院 臨床工学科)
PD13-5溝口勢悟(社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 臨床工学科)
昨今の医療情勢において専門性と分業化が促進される一方で、ハイパーサーミアを取り巻く環境は、臨床工学技士(CE)、診療放射線技師、臨床検査技師、看護師と多職種に渡り業務が行われている。そういった環境においてCEは唯一、職能団体である日本臨床工学技士会において組織的な体制が整備されている。
今回、本セッションでは、病床規模や機能形態の異なる主要5施設の演者より、治療普及に必要となる教育体制、加温技術、多職種連携、経営戦略と多角的な視点から現状の課題も含め報告してもらい、CEの役割を明確化すると共にディスカッションを通じた意識変革を目標に掲げ、ハイパーサーミアの業務確立と更なる飛躍に繋げ組織体制の強化に努めていきたい。
パネルディスカッション14
5月17日(土) 13:40〜15:10 第13会場(10F/会議室1008)
スコープオペレーターで輝くCEの未来 ~ ♡ カメラ持ち。めっちゃ好きやねん!! ♡ ~
座長野澤隆志(杏林大学医学部付属病院)
座長前川正樹(おもと会大浜第一病院 診療技術部 臨床工学科)
コメンテーター塚本真司(社会医療法人 恵佑会 札幌病院)
PD14-1小林美有希(公益財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院 内視鏡センター)
PD14-2宇高大輝(社会医療法人財団大和会 東大和病院 臨床工学室)
PD14-3渡辺貴大(岐阜赤十字病院 臨床工学技術課)
PD14-4山田健留(岡山済生会総合病院 臨床工学科)
PD14-5尾立拓弥(大分県厚生連鶴見病院 診療支援部 臨床工学技術科)
医師の働き方改革に伴う法令改正によるCEのタスク・シフト/シェアが開始され約4年が経過した。スコープオペレーター業務を行う施設は年々増加傾向にある一方、その数は伸び悩んでいる。過去に先進的に業務に介入されていた施設のCEや医師の方々にご講演頂いてきたが、スコープオペレーター業務の今後を考えた際、「これからのCEの未来を担っていく若手が興味を持つこと」は、介入施設の増加に繋がると考えられる。今回、スコープオペレーター業務を実施している若手~中堅のCEの方々に、若手ならではの視点よりスコープオペレーター業務の楽しさ、今後の展望等について講演及びディスカッションを行い未介入施設の方々にもスコープオペレーター業務の楽しさについてより興味を持っていただき、介入施設の増加につながるセッションとしたい。
パネルディスカッション15
5月17日(土) 15:45〜17:45 第13会場(10F/会議室1008)
麻酔関連補助業務のすゝめ ~はやってんの?ほな、うちらもぼちぼち始めてみよか!!~
座長北本憲永(藤田医科大学)
座長上塚 翼(済生会熊本病院)
PD15-1河原香織(日本医科大学付属病院 ME 部)
PD15-2山田健留(岡山済生会総合病院 臨床工学科)
PD15-3西谷裕子(社会医療法人水和会水島中央病院)
PD15-4松本優輝(医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 臨床工学科)
PD15-5加藤貴充(近畿大学病院 臨床工学部)
【麻酔】関連補助業務、最近すごい勢いで広がってきてんねん。ほんでな、今回はその効果を、ここ1~2年で新しく参入してきた施設を中心に紹介してもろて、これから参入しようかなぁって考えてる施設の参考になったらええなぁって思ってんねん。
【関連】するCEのマンパワー問題や、麻酔科医からのNeedsに、どんな形で応えて、労務環境よくしたんか、そんな講演聞かせてもらおかぁって思てんねん。
【補助】の魅力やら可能性やら、おまけに安全管理指針なんかも混ぜて、登壇してもらった人らと色々議論して、麻酔関連補助業務の輪、めっちゃ広げられたらえーなぁ、って夢のあるセッションにしたいねん。
【業務】参入施設、どんどん増えてきたで!はやっとるで!って感じを学会でもアピールして、もっともっと広めていきたいとおもてます。
パネルディスカッション16
5月17日(土) 13:40〜15:10 第14会場(10F/会議室1009)
業務拡大をはじめとする時代背景の変化に対応するための人材育成の課題と対応策 ~日本臨床工学技士会が考える教育支援者の育成~
座長古平 聡(北里大学 医療衛生学部)
座長工藤元嗣(日本医療大学 保健医療学部 臨床工学科)
講師工藤元嗣(日本医療大学 保健医療学部 臨床工学科)
講師塚尾 浩(順天堂大学 医療科学部 臨床工学科)
講師荒川昌洋(地方独立行政法人りんくう総合医療センター 臨床工学)
講師山田紀昭(済生会横浜市東部病院 TQM センター)
近年の業務拡大により、臨床現場でも新人や学生に対する指導の機会が増加している一方、多忙な業務の中での人材育成に課題を抱えている。また、指導を受ける側の若年層(非育成者)においても時代背景の変化やCOVID-19による影響も相まって学ぶ姿勢、働く姿勢が大きく変化しており、指導者層との考え方に乖離を生じている。これらの要因により、これからの指導者には非育成者の状況を分析、把握して適切な指導方法を検討することで、非育成者自身の力で成長できるような支援が求められる。本Sessionでは、養成校および臨床現場の双方から現状の課題と対策事例について報告するほか、日臨工が考えるこれからの指導者(支援者)の育成に対する施策について概説し、課題改善の方策について会場全体でのディスカッションを行うこととした。
パネルディスカッション17
5月17日(土) 15:15〜16:45 第14会場(10F/会議室1009)
CEに最も身近な在宅医療~CEが腹膜透析業務へ参入する方法~
座長安部貴之(東京女子医科大学)
座長平松哲明(名古屋大学医学部附属病院)
PD17-1水野正司(名古屋大学大学院医学系研究科 腎不全システム治療学寄附講座 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科)
PD17-2西津 規((一財)平成紫川会 小倉記念病院 看護部)
PD17-3阿部政利(医療法人社団聖医会 せいいかいメディカルクリニックOYAMA)
PD17-4林滉一郎(聖マリアンナ医科大学病院 臨床工学技術部)
PD17-5元山勇士(善仁会グループ 臨床工学部)
PD17-6金 学粋(聖路加国際病院 臨床工学科 日本臨床工学技士会 腹膜透析業務検討ワーキンググループ)
コメンテーター吉川史華(川崎医科大学附属病院 ME センター)
コメンテーター髙橋真理子(日産厚生会玉川病院)
高齢化に伴い国をあげて在宅医療を推進している中、CEには医療機関だけでなく在宅医療への参入を求める声も多く、その中で腹膜透析(PD)関連機器管理や遠隔モニタリング機能が搭載され診療報酬が新設され、腹膜透析認定指導臨床工学技士制度の誕生するなど、PDが注目を集めている。
実態報告では、CEがPD介入した理由は「他職種からの要望」が最も多く、PD領域は業務拡大が期待されている分野である。しかし現状ではCEの関与率は増加傾向ではあるものの、「業務実態報告2023」では23.9%で、今後さらに積極的な関与が必要となってくる。
今回のセッションでは他職種の立場からCEに期待することや関わって欲しい業務、どのようにPD業務へ参入したかを紹介し、腹膜透析におけるCEの役割や可能性について議論を深めたい。
パネルディスカッション18
5月17日(土) 16:50〜18:20 第14会場(10F/会議室1009)
高気圧酸素治療(HBO)装置の新規導入施設に対する提言~HBOを始めるために必要なこと~
座長太田雅文(医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院)
座長野堀耕佑(公立陶生病院)
PD18-1坂上正道(済生会熊本病院 臨床工学部門 日本臨床工学技士会 高気圧酸素治療業務検討小委員会 委員 日本高気圧潜水医学会 技術部会安全対策委員会 委員長)
PD18-2柏原 謙(京都桂病院 臨床工学科)
PD18-3片山浩二(一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 臨床工学課)
PD18-4東山智香子(香川大学医学部附属病院 医療技術部臨床工学部門)
PD18-5灘吉進也(社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 臨床工学科)
高気圧酸素治療(HBO)では2018年の診療報酬改定以降、救急・非救急の撤廃や大幅な保険点数の見直しに伴い導入施設数は徐々に増加しており、これまでHBO装置の設置施設数は減少の一途を辿り続け風前の灯と揶揄された状況に変化が生じている。
しかし、いざHBOを開始しようとする導入希望施設においては、診療体制の構築に向けて装置の機種選定や付属機器の有無、施設・設備の整備など、専門的なアドバイスの相談窓口がなく困っている状況が示唆される。
そのため、今回HBO装置の新規導入を検討している施設と、新規導入した施設を対象に「HBO新規導入施設に対する先駆者からの提言」をテーマに掲げ、新規導入のポイントから今後の適切なHBOの運用が図れるよう協議を図りたい。
パネルディスカッション19
5月17日(土) 9:00〜10:30 第17会場(12F/特別会議場)
医療DX・AIとセキュリティ対策
座長森實篤司(HOSPY 腎透析事業部)
座長川崎路浩(神奈川工科大学)
PD19-1肥田泰幸(東都大学 幕張ヒューマンケア学部 臨床工学科)
PD19-2小林 駿(JA 長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター)
PD19-3宮下沙織(国民健康保険富士吉田市立病院臨床工学科)
PD19-4岸本和昌(京都大学医学部附属病院 医療情報企画部 京都大学大学院 情報学研究科 京都大学大学院 医学研究科)
本委員会では、過去の日臨工で複数回にわたり、サイバーセキュリティに関するシンポジウムを企画して、その啓蒙活動をおこなった。
近年、わずかながら臨床工学技士の関わる医療現場でセキュリティを意識した取り組みがはじまっている。
まだまだ、少ない事例ではあるが着実に前進している取り組みを紹介して、さらなる普及と啓発につなげたく、本内容を企画した。
パネルディスカッション20
5月17日(土) 10:35〜12:05 第17会場(12F/特別会議場)
実録!!!ワークライフすごろく 〜ライフイベントと自分の価値観との調和を目指して〜
司会須賀里香(埼玉医科大学総合医療センター)
司会杉原尚枝(社会医療法人 彩樹 豊中敬仁会病院)
講師岩本 渚(佐賀県医療センター好生館)
講師宮川幸恵(独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター)
講師山田紀昭(済生会横浜市東部病院)
講師竹内記代(一般社団法人 杏仁会 江南病院)
講師前川正樹(おもと会大浜第一病院 診療技術部 臨床工学科)
ファシリテーター石塚后彦(山形県立中央病院 臨床工学部)
ファシリテーター亜厂耕助(東京都立神経病院 麻酔科)
ファシリテーター滝口尚子(北良株式会社)
ファシリテーター宮本 直(独立行政法人国立病院機構東京病院 麻酔科)
ファシリテーター上田貴美子(済生会吉備病院 臨床工学科)
ファシリテーター平野恵子(JA 広島総合病院 臨床工学科)
ファシリテーター南部由喜江(神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター)
ファシリテーター伊東朋子(大阪医専)
【キーワード】2つの視点、多様な働き方、価値観の理解と調和、生活と仕事の好循環
当会の組織力強化・連携推進に向け、全会員が他人事にならず、従来の働き方から多様な働き方、世代別やそれぞれの価値観を知り理解し認め合うことで、調和のとれた組織づくりからこれからの未来に向けた働き方の創造に繋げていきたい。また、組織においても、実現に向けて必要となる制度の新設や従来の制度の改定などに目を向ける一助となることを目的とする。獲得目標として、①若い人には、これから起こるかもしれないライフイベントを予習感覚で学んで頂く。
②もし自分のライフイベントが過ぎている場合でも、現代の20代、30代の話を聞き、部下や後輩の関わり方を考えて頂く。セッションはワールド・カフェ形式で行う。