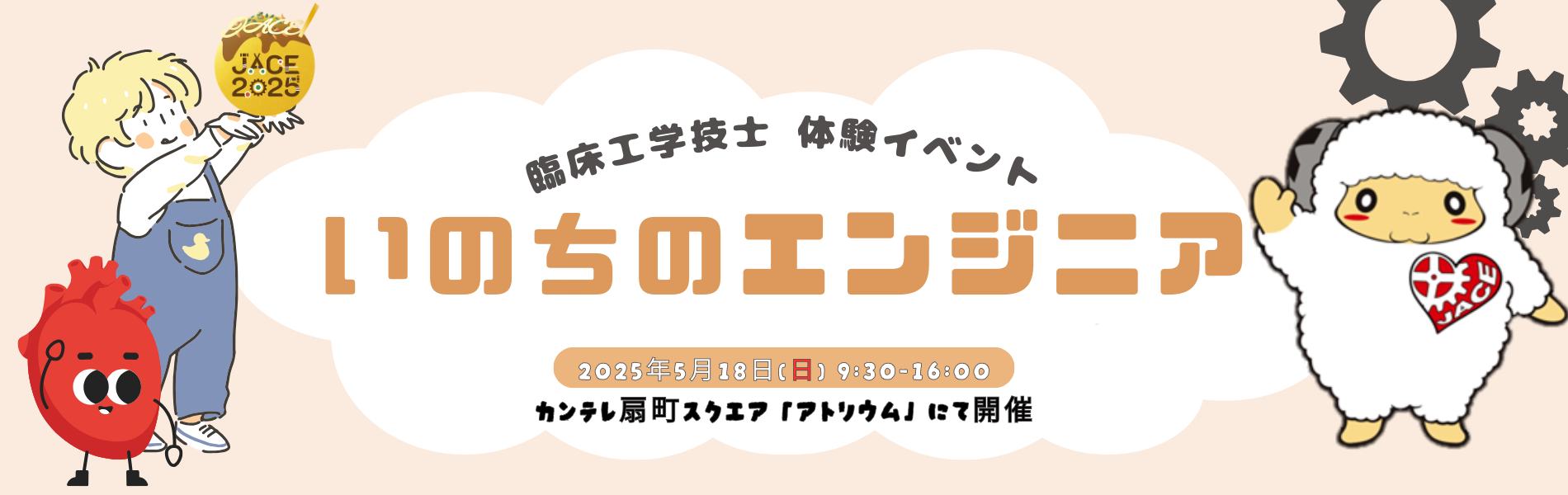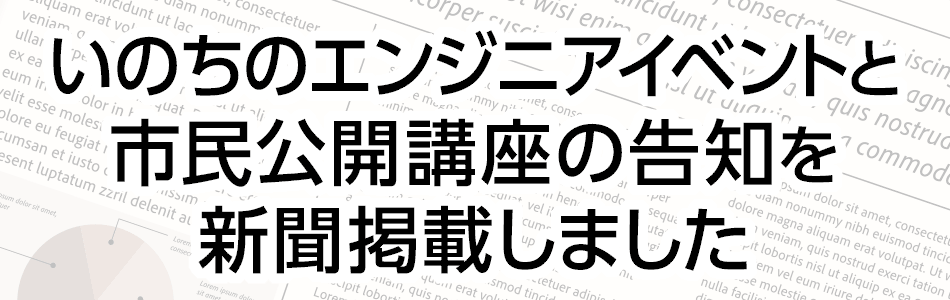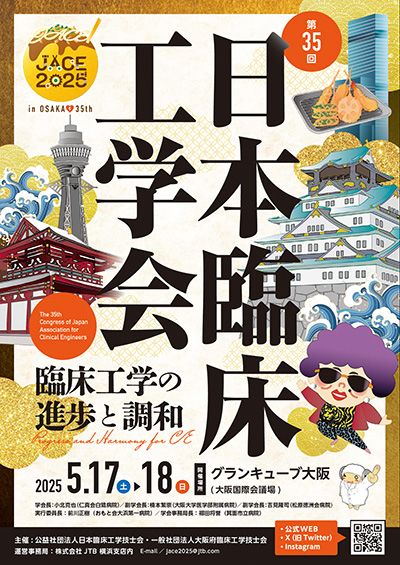シンポジウム1〜10
シンポジウム1
5月17日(土) 13:40〜15:40 第1会場(5F/大ホール)
業務実態報告からみた臨床工学の進歩と調和
座長五十嵐茂幸(北陸大学 医療保健学部 医療技術学科 准教授)
座長岸上香織(医療法人 厚生会 福井厚生病院 臨床工学課 課長)
「業務実態報告からみた臨床工学の進歩と調和 ~2024年度業務実態報告 個人報告編~」
「業務実態報告からみた臨床工学の進歩と調和 ~2024年度施設基本報告より~」
「医学研究における統計学の基礎と主要な検定方法」
「医学研究における統計解析の実践~母集団推定・群間比較・要因分析を中心に~」
業務実態報告2024の結果を踏まえテーマ臨床工学の進歩と調和に沿った内容をクローズアップして報告し、統計の基本講演、事例を踏まえた統計手法の選択の講演を行う。
シンポジウム2
5月17日(土) 10:05〜12:05 第2会場(5F/小ホール)
診療報酬からみた臨床工学技士の将来像
座長野村知由樹(医誠会都志見病院 臨床工学部/公益社団法人 日本臨床工学技士会診療報酬等委員会 技士長/担当理事)
座長荒木康幸(済生会熊本病院 臨床工学部門/公益社団法人日本臨床工学技士会診療報酬等委員会 統括技師長兼臨床工学部門技師長/委員長)
基調講演今村知明(公立大学法人 奈良県立医科大学 公衆衛生学講座 教授)
演者掛地吉弘(神戸大学大学院医学研究科 外科学講座食道胃腸外科学分野 教授)
演者安中正和(医療法人 安中外科・脳神経外科医院 脳神経外科 理事長)
演者野村知由樹(医療法人 医誠会都志見病院臨床工学部 技士長 公益社団法人日本臨床工学技士会診療報酬等委員会 担当理事)
コメンテーター萱島道徳(東亜大学 医療学部 医療工学科 特任教授)
診療報酬獲得と業務の拡大は切っても切れないものである。今回、県立奈良医大の今村先生に医療政策全般のお話しを頂戴し、併せて過去にさかのぼり、「医師の働き方改革におけるタスクシフト・シェア」検討時、業務追加のための臨床工学技士法改正への経緯について、基調講演としてご登壇いただく。その後、当会が診療報酬獲得に力を入れている手術室分野、在宅医療分野における臨床工学技士への期待について、各専門学会の先生からご講演をいただく。最後に当会診療報酬等委員会担当理事より当会が考えている診療報酬の獲得に向けた具体的な内容を報告し、会場を交えたディスカッションを行う。
シンポジウム3
5月17日(土) 17:20〜18:20 第2会場(5F/小ホール)
法改正から4年経過した今のアブレーション業務の実態に迫る
座長堺 美郎(社会福祉法人 恩賜財団済生会熊本病院 臨床工学部 係長)
座長谷岡 怜(神戸大学医学部附属病院 臨床工学部 主任臨床工学技士)
「不整脈に対するカテーテルアブレーション治療における臨床工学技士の必要性」
井上耕一(国立病院機構大阪医療センター 循環器内科 科長)
「法改正から 4 年経過した今のアブレーション業務の実態に迫る」
縮 恭一(筑波大学附属病院 臨床工学部)
コメンテーター野村知由樹(日本臨床工学技士会 常任理事・医療法人医誠会 都志見病院)
令和3年の臨床工学技士法の改定によって不整脈アブレーションにおける高周波通電操作は臨床工学技士の業務範囲として明確となった。しかしながら、臨床においては全ての不整脈アブレーションの現場に十分な人数の臨床工学技士が配置されている、とは言えない。その理由は何なのか?何を改善すれば状況が変わるのか?業務体制や人員、コストの問題はどのように取り組むべきなのか?実際に手技を行う不整脈専門の医師達はどう思っているのか?
日本不整脈心電学会からアブレーション委員長をお招きしてディスカッションしたい。
シンポジウム4
5月17日(土) 9:00〜10:30 第12会場(10F/会議室1006・1007)
臨床工学の国際的「調和」を考える
座長川崎忠行(前田記念腎研究所茂原クリニック 臨床工学部 部長)
司会福田勇司(松江赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 課長)
「日中技術交流事業について」
園川龍毅(臨床工学国際推進財団 理事兼事務局長)
「途上国におけるCE(ME)育成を通した「国との国際的調和」」
楢村友隆(倉敷芸術科学大学 環境生命科学科・臨床工学国際推進財団)
「国際組織等とのハーモナイゼーション」
福田恵子(大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部 未来医療センター)
「クリニカルエンジニアとの国境を超えた調和が生む新たな可能性」
平山隆浩(岡山大学学術研究院 医歯薬学域 地域二次救急・災害医療推進講座・日本臨床工学技士会国際交流委員会)
先進医療機器の発展という側面から、臨床工学の需要性が論じられ、1980年以降、教育や資格認定制度の確立とともに世界各国でクリニカルエンジニア団体が誕生している。この制度自体は世界的に共通だが、これを支える法制度は国によって異なる。こうした「教育や法的調和」の必要性は、各国の学会団体においても強く認識されている。実質的に国家資格を有する日本が教育や法的環境作りを先導することが重要と考える。日本には臨床工学技能の資質向上や医療機器の信頼性向上に努める日本臨床工学技士会と臨床工学技術の海外への普及啓発により保健・医療の向上に努める臨床工学国際推進財団がある。各々の国際活動の先駆者複数人が意見・知見を述べ、討論を行い、臨床工学の発展、支援のために今後の海外団体との国際的「調和」の在り方を提示する。
シンポジウム5
5月17日(土) 15:45〜17:45 第12会場(10F/会議室1006・1007)
末梢血管内治療の現在・未来 ~タスクシフト・シェアを活かす~
座長倉田直哉(大阪けいさつ病院 臨床工学科 係長)
座長山口裕司(広島市立北部医療センター安佐市民病院 臨床工学室 主任技師)
「末梢血管内(下肢血管・脳血管)治療の現在・未来 -タスクシフト・シェアを生かす-」
飯田 修(大阪けいさつ病院 循環器内科)
「きっとあなたも沼落ちする!脳血管内治療のセカイ」
松重俊憲(広島市立北部医療センター安佐市民病院 脳神経外科・脳血管内治療科)
コメンテーター矢津優子(野崎徳洲会病院 臨床工学科)
コメンテーター吉田勇斗(医療法人美脳 札幌美しが丘脳神経外科病院 臨床工学科)
2024年に厚生労働省医政局医事課より、(「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」等に関するQ&Aについて)、という文章が各都道府県衛生主管部(局)に通達された。その中で心臓・血管カテーテル業務における清潔野業務に関して明記されており、血管カテーテル業務の中には脳血管や下肢血管も含まれている。臨床現場においても通達を踏まえ、タスクシフト・シェアを進めていかなければいけないが、いかに進めていくか、どのように取り組んでいくか。など多くの悩みを抱える施設も少なくないと考える。そこで各領域のトップオペレーターの先生に、各領域でタスクシフト・シェアをうまく進めていく方法・CEに求めるもの・今後取り組むべきこと、などを講演していただく。
シンポジウム6
5月17日(土) 16:20〜17:50 第16会場(12F/会議室1202)
日本集中治療医学会合同企画「集中治療専門臨床工学技士の誕生から将来へ」
座長木村政義(兵庫医科大学病院 臨床工学部 臨床工学技士)
座長千原伸也(日本医療大学 保健医療学部 臨床工学科 教授)
演者相嶋一登(横浜市立市民病院 臨床工学部)
演者佐々木慎理(川崎医科大学附属病院 ME センター)
演者礒本泰輔(兵庫医科大学病院 臨床工学部)
演者江木盛時(京都大学医学部附属病院 麻酔科 集中治療部)
演者河合佑亮(藤田医科大学病院 看護部)
集中治療に関する認定制度は、日本臨床工学技士会の集中治療認定臨床工学技士とその上位認定として日本集中治療医学会の集中治療専門臨床工学技士で構成されており、2つの団体が連携して卒後教育を担っている。新型コロナウイルスパンデミックを経験し、集中治療における臨床工学技士の重要性が認識される中、集中治療専門臨床工学技士の誕生から将来展望までを討論する。
シンポジウム7
5月17日(土) 13:40〜15:40 第17会場(12F/特別会議場)
専門・認定臨床工学技士取得の実際と他団体との連携を視野に入れた今後の展望
座長山下芳久(公益社団法人 日本臨床工学技士会 副理事長)
座長堀 純也(日本臨床工学技士会 専門・認定検定委員会・岡山理科大学 生命科学部 医療技術学科)
「公益社団法人 日本臨床工学技士会 専門臨床工学技士認定制度について」
配野 治(日本臨床工学技士会 専門・認定検定委員会担当理事・千葉メディカルセンター 臨床工学部)
「CBT による専門・認定検定試験の出題形式の実際」
堀 純也(日本臨床工学技士会 専門・認定検定委員会・岡山理科大学 生命科学部 医療技術学科)
「「認定CE」手術試験の新設について」
菊地 徹(公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 技術部門 臨床工学室・公益社団法人日本臨床工学技士会 手術関連検定小委員会)
「「認定CE」医療安全が目指すもの」
本田靖雅(社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 臨床工学室・公益社団法人 日本臨床工学技士会医療安全検定小委員会)
「集中治療専門臨床工学技士制度について~臨床工学技士認定制度における学会との連携~」
相嶋一登(横浜市立市民病院 臨床工学部)
「専門手術臨床工学技士を取得した経験」
篠崎太一(済生会兵庫県病院 臨床工学科)
「認定臨床工学技士取得をふりかえって」
片岡祐美(医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 臨床工学科)
日本臨床工学技士会では,ひとりひとりの臨床工学技士が各領域の業務内容を適切に把握し,指導的立場で専門的治療の対応ができる能力を修得することを目的として専門・認定臨床工学技士制度を設けている。多くの場合,これらの資格は個人の自己研鑽という位置付けとして認識されている。しかし,認定・専門資格は個人の能力を証明するためのものにとどまらない。認定・専門資格をもった臨床工学技士が増えることは,他学会との連携促進や診療報酬獲得への礎ともなる。
当セッションでは,専門・認定資格の取得を検討している方への情報提供を行うと共に,今後新設される「認定手術臨床工学技士」,「認定医療安全臨床工学技士」制度の概要,他団体との連携の重要性,実際に認定資格,専門資格を取得した方の経験談を踏まえてディスカッションを行う。
シンポジウム8
5月18日(日) 8:30〜10:00 第2会場(5F/小ホール)
急性血液浄化の進歩と調和
座長三木隆弘(日本大学病院 臨床工学室 技士長補佐)
座長千原伸也(日本医療大学 保健医療学部 臨床工学科 学科長)
「持続的腎代替療法における前希釈法の有用性」
島田朋和(札幌医科大学附属病院 臨床工学部)
「急性血液浄化領域におけるPS 膜への新しい試みと期待できること」
山中光昭(日本大学病院 臨床工学室)
「敗血症の病態から見たサイトカイン吸着膜を選択する意義」
峰松佑輔(大阪大学 医学部附属病院 臨床工学部)
「敗血症に対する血球細胞除去用浄化器「Adacolumn」を用いた免疫制御血液浄化システムの進歩と調和」
清水弘太(藤田医科大学病院 臨床工学部)
急性血液浄化領域におけるデバイスや治療法の進歩は目紛しく、ただ単に敗血症患者や急性腎障害を呈する患者に血液浄化を実施すれば良いという訳ではなく、患者さんにとって優しい(調和)血液浄化も求められています。
まさに本学術集会のテーマである『進歩と調和』に相応しいと考え、本シンポジウムのテーマを『急性血液浄化の進歩と調和』としました。
本セッションでは、急性血液浄化領域における最先端のトピックをまじえながら『急性血液浄化の進歩と調和』についてディスカッションしたいと考えています。
シンポジウム9
5月18日(日) 13:10〜15:10 第2会場(5F/小ホール)
総務省近畿総合通信局合同セッション:病院機能評価で求められる病院内電波管理体制の構築~医用テレメータを中心に~
座長加納 隆(滋慶医療科学大学大学院 医療管理学研究科)
座長宮本哲豪(淀川キリスト教病院 臨床工学課 課長)
「医療機関における安心・安全な電波利用の推進-病院機能評価で求められる病院内電波管理の要点-」
色部俊昭(総務省 電波部電波環境課)
「EMCC 発行「医用テレメータの電波管理実践ガイド」の概要」
加納 隆(滋慶医療科学大学大学院 医療管理学研究科)
「医用テレメータの電波管理における実際と課題」
松月正樹(三重大学医学部附属病院 臨床工学部)
「医療安全から見た医用テレメータの電波管理」
酒井基広(東京女子医科大学病院 医療安全推進部)
「医用テレメータの電波不感エリア調査とその対策」
新 秀直(東京大学医学部附属病院 企画情報運営部 企画経営部 病院長補佐)
病院内では電波を利用する医用テレメータのほかに、無線LANや携帯電話等の情報通信機器の普及も目覚ましい。しかし、電波の利便性とは裏腹に、医用テレメータの電波不到達などの電波に起因する医療事故も報告されている。そこで、総務省は厚生労働省と連携して電波環境協議会のもとで詳細な検討を行い、平成28年に「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き」を発行し、さらにその改定版を令和3年に発行した。しかし、電波管理体制の構築に取り組んでいる施設は未だ少ないのが現状である。本セッションでは、病院機能評価3rdG_ver3.0における評価項目に電波利用に係る内容が取り入れられたことを機に、具体的にどのように電波管理体制の構築を進めればいいか、特に医用テレメータの電波管理を中心に考えてみたい。
シンポジウム10
5月18日(日) 13:10〜15:10 第13会場(10F/会議室1008)
臨床工学技士の認知度向上に対する問題点と取組みについて ‐施設協議会の視点と臨床工学技士会の視点から‐
座長藤江建朗(森ノ宮医療大学 医療技術学部臨床工学科 教授)
座長春田良雄(公立陶生病院 技師長)
「臨床工学技士の未来—成長か衰退か?社会構造の変化と職能向上への課題」
小野淳一(川崎医療福祉大学 医療技術学部臨床工学科)
「臨床工学技士の人材育成を担う高等教育機関が設置されていない地域にある大学病院の臨床工学部門としての役割」
道永祐希(信州大学医学部附属病院 臨床工学部・信州大学医学部附属病院 医療機器統括管理室)
「動画系SNS(TikTok 等)を活用したCE の認知度向上戦略(現状、成果、今後の展望)」
大河原崇文(国際メディカル専門学校 教務部 臨床工学技士科・日本臨床工学技士教育施設協議会 広報委員会)
「広報活動の未来を拓く若手の力!認知度UPへの戦略と課題」
岡田未奈(済生会西条病院・日本臨床工学技士会 人材活性化委員会)
「臨床工学技士の認知度向上に対する問題点と取組みについて-施設協議会の視点と臨床工学技士会の視点から-」
西手芳明(近畿大学 生物理工学部 医用工学科)
「愛知県臨床工学技士会の臨床工学技士認知度向上への取り組み」
黒川大樹(小牧市民病院 管財課)
今回のシンポジウムでは、医療機関、施設協議会や日本臨床工学技士会から広報担当者などが一堂に会し、先進的な取り組み事例、直面する課題や失敗と思う事例について深く掘り下げていきます。SNSを活用した戦略的な情報発信、医療現場と地域を結ぶ啓発活動、次世代を担う未来のCEへの広報など、多角的な視点で行っている広報についてアプローチや問題点について共有します。
さらに、職種の認知度向上に向けた効果的な戦略とは何か、会場の皆さんと共に考える貴重な機会だと思っています。
広報に困っている都道府県技士会の広報担当者の方、将来、教員を目指している方、CEの認知を向上するためにはどうしたらいいのかを常に考えている方、とりあえず聞いてみたい方、ぜひご参加ください。